京都・伏見稲荷大社「外拝殿」【重要文化財】
創建年
- 1589年(天正17年/安土桃山時代)
再建年
- 1840年(天保11年/江戸末期)
社殿の大きさ
- 桁行(長い面:横幅)五間(約9m)
- 梁間(短い面:奥行)三間(約5.5m)
建築様式(造り)
- 入母屋造
屋根の造り
- 檜皮葺
重要文化財指定年月日
- 2014年(平成26年)1月27日
外拝殿にて執行される行事
- 春と秋の献花祭
- 様々な神振行事
伏見稲荷大社・外拝殿の読み方
外拝殿の読み方は「げはいでん」と読みます。
外拝殿の名前の由来
京都・伏見稲荷大社には大型の拝殿が2つ存在します。
普段の日常、参拝者が手を合わせてお祈りを捧げる場所です。
![]() 2つ目の拝殿が、この外拝殿です。
2つ目の拝殿が、この外拝殿です。
お分かりのように内側の拝殿が内拝殿とするならば、外側の拝殿がこの外拝殿とな〜る。
外拝殿の役割りと外拝殿で執行される有名行事
外拝殿は毎日使用はされていないが、前述の通り、名称に「拝殿」が付されることから、拝殿(礼拝する場所)となる。
なお、現状の外拝殿はその内側に内拝殿があることから、拝殿のみとしては利用されておらず、たとえば舞踊(お神楽)などが奉仕されることもあ〜る。
節分祭
2月の節分祭(2月節分の日)での「豆まきの舞台」として使用される。
- 神事開始時間:午前09時
節分とは、元来、春夏秋冬の季節毎の境目を節分といったが、現在、単に「節分」といえば、冬と春の年2回の節分を指す。
昔は季節の変わり目は気象・気候が不安定になり、その結果、生活にも害が及んで身体を蝕むとされた。
それゆえ、節分の日には節分祭を執行し、除疫・招福を祈念する。
🦊豆まき神事
以下の時間になると外拝殿にて福男福女及び福娘による豆まき行事が催される。
- 節分祭の終了後
- 11時30分
- 13時00分
以上の3回。
特に豆(まめ)は摩滅(まめ)に通じるがあるものがあるとし、古来、霊力が宿るとされる。
穀物の神を奉斎する伏見稲荷大社の豆まきは他とは少し色々な面で違いがありそぅな気はする。
献花祭
以下、春と秋の献花祭でも使用され〜る。
🦊神事開始時間
- 春(4月1日):午前09時
- 秋(11月1日):午前11時
🦊春の献花祭
外拝殿にて池坊華道会による献花の儀が催され〜る。
🦊秋の献花祭
外拝殿にて嵯峨 御流華道 総司所(旧嵯峨御所 大覚寺 門跡)による献花の儀が催され〜る。
稲荷祭
5月の稲荷祭では5基の神輿の御旅所として外拝殿の前に並ぶ。
関連記事:![]() 【#x1f98a;稲荷祭】日程(期間・時間or神輿渡御ルート)や歴史(起源)を……クレーンGしながら知る構想❓
【#x1f98a;稲荷祭】日程(期間・時間or神輿渡御ルート)や歴史(起源)を……クレーンGしながら知る構想❓
関連記事:![]() 伏見稲荷大社「御旅所(おたびしょ)」の境内見どころ(御朱印・歴史など)を…空想してたの❓
伏見稲荷大社「御旅所(おたびしょ)」の境内見どころ(御朱印・歴史など)を…空想してたの❓
外拝殿の建築様式
外拝殿は他の社殿とは建築様式が異なり、四方に壁がなく吹き放ち(内部がパンツ丸見え状態❤️)になっていることからも分かるように神楽・舞踊がしやすぃように、見やすいにように舞台としての設計もされてい‥‥申す。にゃ
外拝殿の見どころはココ!「吊り灯籠の黄道12星座」
昼間、伏見稲荷大社へ参拝に訪れるとあまり目立たないので、素通りしてしまいますが、外拝殿をよく見ると軒下に燈籠が吊られているのが分か〜る。
この燈籠は12基吊るされており、十二支ではなく十二宮(黄道の十二星座)を表すのが、異例として注目されてい‥‥ます。耐 ふぅ
聞くところによると、法隆寺、大原三千院、東寺(宝菩提院)などの星まんだら(曼荼羅)に釈迦像とともに描かれている例はあるも、黄道十二星座のみを独立させて工芸化した意匠は他に類例がなく、明治時代の美術史上、稀に見られる秀作であり、世界的に評価を受けているらしい。
平野英青氏の制作で、材質は鉄。1906年(明治三十九年)に稲垣藤兵衛宇治が寄贈したものと伝わる。
黄道とは?
黄道十二星座の「黄道(こうどう)」とは、太陽の軌道のことであり、太陽がその日1日に通る「軌道」のこと。
また、黄道十二星座とは太陽の軌道上に存在する星座のこと。
星座は本来13座あるが、太陽の軌道上に存在しない「へびつかい座」を除いた12座のことを「黄道十二星座」と称す〜る。
 黄道12星座 一覧
黄道12星座 一覧
上記の星座を象徴する動物などが象られた燈籠が12基ブラさがっていることになります。
通例であれば、干支を用いることが多いのですが、星座を用いる例は非常に少なく、大変めずらしいものです。
たとえば、日光東照宮を例に挙げると社殿の周囲に代々の将軍の干支を蟇股に彫り込んでいます。
この中でも分かりにくいのが、「おひつじ座」「おとめ座」「さそり座」の吊り灯籠です。(描かれている模様が分かりにくい。)
伏見稲荷大社・外拝殿の歴史
現在の外拝殿は1840年(天保十一年)の再建後の姿となるが、昭和三十六年に本殿前に内拝殿が建てられたために今日、この拝殿は「外拝殿」と呼ばれる。
稲荷祭にてまだ神輿が氏子たちに担がれていた時代、神幸祭(しんこうさい)前日になると宵宮(よいみや)と称し、荘厳華麗な5基の神輿がこの外拝殿の舞台上に置かれたらしい。
往時は内部に三十六歌仙の額が飾られていたらしいが、現在は別場所にて収蔵される。
外拝殿の建築様式(造り)
伏見稲荷大社の外拝殿は、催しを披露するかの如く、四方が吹き放ちになっており、簡素な舟肘木で組み上げられています。
屋根は入母屋造に檜皮で葺きこみ、四隅にわずかな軒反りが見えます。
飾り金具や朱漆の塗装など、本殿に倣った様式がうかがえます。
伏見稲荷大社は和様建築
伏見稲荷大社境内の社殿は朱色を基調とし、黄土を木口に塗り込んだり、中備に組み物を用いないことや、この外拝殿の欄干(らんかん)のように親柱で横材をまとめて収容している点、本殿に連子窓をハメ込む点や蟇股を多用する点などを挙げると、和様建築の特徴が色濃くみられる。
伏見稲荷大社・外拝殿の場所(地図)
伏見稲荷大社の境内入口の楼門をくぐり抜けて目の前に位置します。
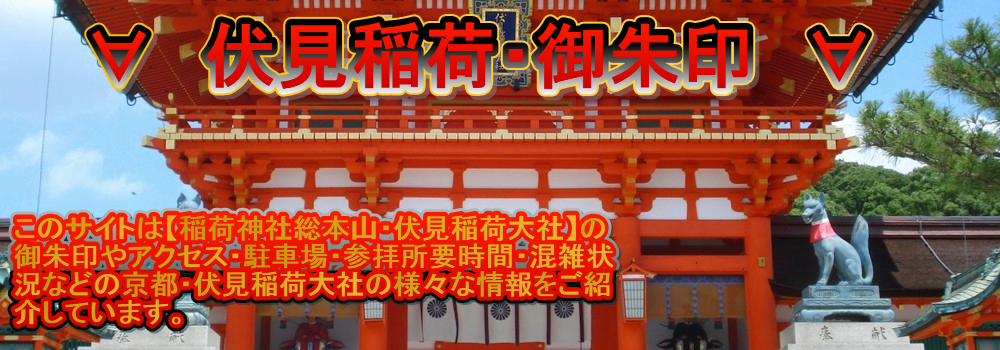

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)